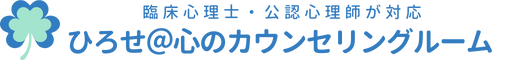愛着障害には種類がある?大人と子どもの症状について
愛着障害という言葉は、心理学と医学での定義や考え方が少し異なることはご存じでしょうか?
医学的な愛着障害は、広義的な心理学の意味するものとは違い、限定的だと言われているのです。
そこで今回は、医学的定義での愛着障害の種類や特徴、大人の愛着障害の特徴についてお伝えしていきます。
目次
愛着障害の種類・特徴
愛着障害とは、養育者との愛着がうまく形成されず、子どもの情緒や対人関係に問題が生じる状態のことを言います。
そして、医学的定義では「反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)」と「脱抑制型愛着障害」の2種類のタイプに分けられ、その症状が“5歳以前に発症する”とされているのです。
ここでは、それぞれのタイプの愛着障害について特徴を解説していきます。

反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)
反応性アタッチメント障害は、人に対して過剰に警戒するタイプのことで、周囲に対して無関心であったり、人に頼るということができなかったりします。
原因としてあげられる環境は、養育者による虐待、ひどい無視、ネグレクト、無関心など。
症状が自閉症スペクトラム障害ともよく似ているため、判断が難しいとも言われています。
- 人を信用できない
- 喜びや悲しみを表情に出さない
- 他の子どもとの交流がない
- 恐怖心や警戒心が強い
- 人の言葉に傷つきやすい
- 自己肯定感が低い
- いつも脅えている

脱抑制型愛着障害
脱抑制型愛着障害は、人に対して過剰なほど馴れ馴れしくするタイプのことで、誰に対しても甘えた態度を取ります。
特定の養育者とうまく愛着が形成されなかったことによって、注意を引こうと行動する場面がよく見られるのも特徴のひとつです。
症状としては、注意欠如・多動症(ADHD)とよく似ています。
- 誰にでも抱き着く
- 馴れ馴れしくして注意を引こうとする
- 落ち着きがない
- わがままな言動が多い
- 嘘をよくつく
- 乱暴な言動がある
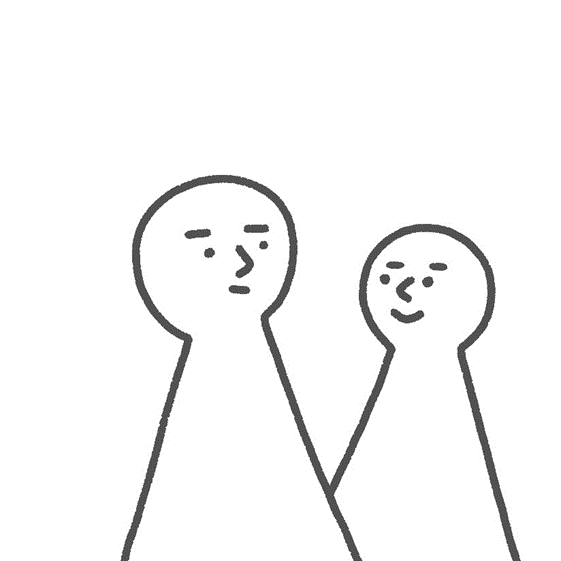
どちらにも共通する特徴
愛着障害のある子どもは、「反応性アタッチメント障害」と「脱抑制型愛着障害」に分類されます。
そして、このふたつは正反対の特徴を持っていますが、中には共通する特徴もあるのです。
- 髪の毛を抜く、引っ搔くなどの自傷行為
- 他人を傷つける他害行為
- 食べる量が少ない
- 十分な睡眠がとれていない
- 体調不良を起こしやすい
- 大人を試す言動がある
- 意地っ張りになる
反応性アタッチメント障害と脱抑制型愛着障害は、どちらも養育者との十分な愛着形成ができていないことによって起こるため、上手に甘えることができません。
また、子どもの愛着障害は、どちらのタイプであっても症状が発達障害とよく似ているため、専門家ですら判断が難しいこともあります。

大人の愛着障害の種類・特徴
5歳以前に症状が見られる「愛着障害」ですが、大人になってからも症状が改善されないケースもあります。
人とコミュニケーションがうまく取れなかったり、ちょっとしたことで深く傷ついてしまったり、怒りをコントロールできなかったりするなど。
そういった症状を抱えたまま成長した場合は、「大人の愛着障害」と呼ばれています。
そしてこの「大人の愛着障害」は、医学的なものではなく心理学用語のため、子どもの愛着障害のように種類を明確に分けられていません。
そんな大人の愛着障害の特徴は、子どもの症状とはまた異なるため、ここで詳しく解説していきます。
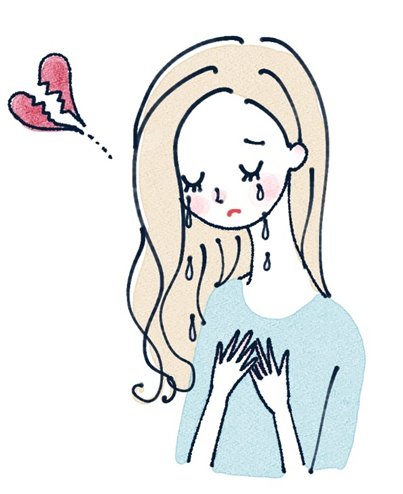
情緒面が不安定
乳幼児期に養育者と愛着が形成されなかった場合、大人になってからも情緒が不安定になってしまいます。
怒りをコントロールできず、すぐにカッとなったり、他の人からすると些細なことで傷ついたりすることも多いです。
そのため、周囲の人から「建設的な話し合いができない人」といったイメージを持たれる場合もあります。
人間関係でトラブルを抱えやすい
愛着障害を抱えたまま大人になった場合、嫌われることを恐れて極端に人の顔色をうかがったり、ほどよい距離感がわからずコミュニケーションがうまく取れなかったりします。
そういった対人関係での特徴は、プライベートだけでなく仕事にも影響するため、トラブルを抱えることもあるでしょう。
アイデンティティの確立がうまくいっていない
幼少期の愛着形成は、大人になってからのアイデンティティの確立にも影響が出ます。
自己肯定感が低く、自分を信じることができないため、ひとりで決断することに不安を感じてしまうのです。
進学先や就職先を決めるなど、人生の大きな決断を迫られたときも、「自分がどうしたいのかわからない」という状態になってしまいます。

大人の愛着障害で悩んだときはカウンセリングへ
愛着障害は医学的な定義では、「反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)」と「脱抑制型愛着障害」の2種類に分けられ、5歳以前に発症するとされています。
一方心理学用語としての愛着障害は、幼少期のみならず大人になってからも、その症状によって生きづらさを感じている人のことも含んでいます。
愛着障害の特徴は、発達障害ともよく似ていて判断が難しい部分もあるため、「愛着障害のような症状がある」と悩んでいる方は、ぜひ専門機関で診断を受けてみましょう。
当カウンセリングルームでは、愛着障害の方を対象としたオンラインカウンセリングを実施しております。
仕事や家庭、日常生活などで感じる生きづらさやお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
11月先着3名様
初回カウンセリング
45分 5,000円
※はじめての方は初回カウンセリングをお申込みください。
※初回はオンラインでカウンセリングを行っています。Zoom・Skype・Line通話でのカウンセリングが可能です。
※初回カウセリングでは、現在のあなたの状態をお伺いして、今後の目標や方針を決めていきます。
LINEでのご相談
愛着障害や強迫性障害、不安障害のご相談を受け付けています。
HSPやアダルトチルドレンのお悩みの方やカウンセリングご希望の方は、友達追加ボタンを押して、メッセージをお送りください。
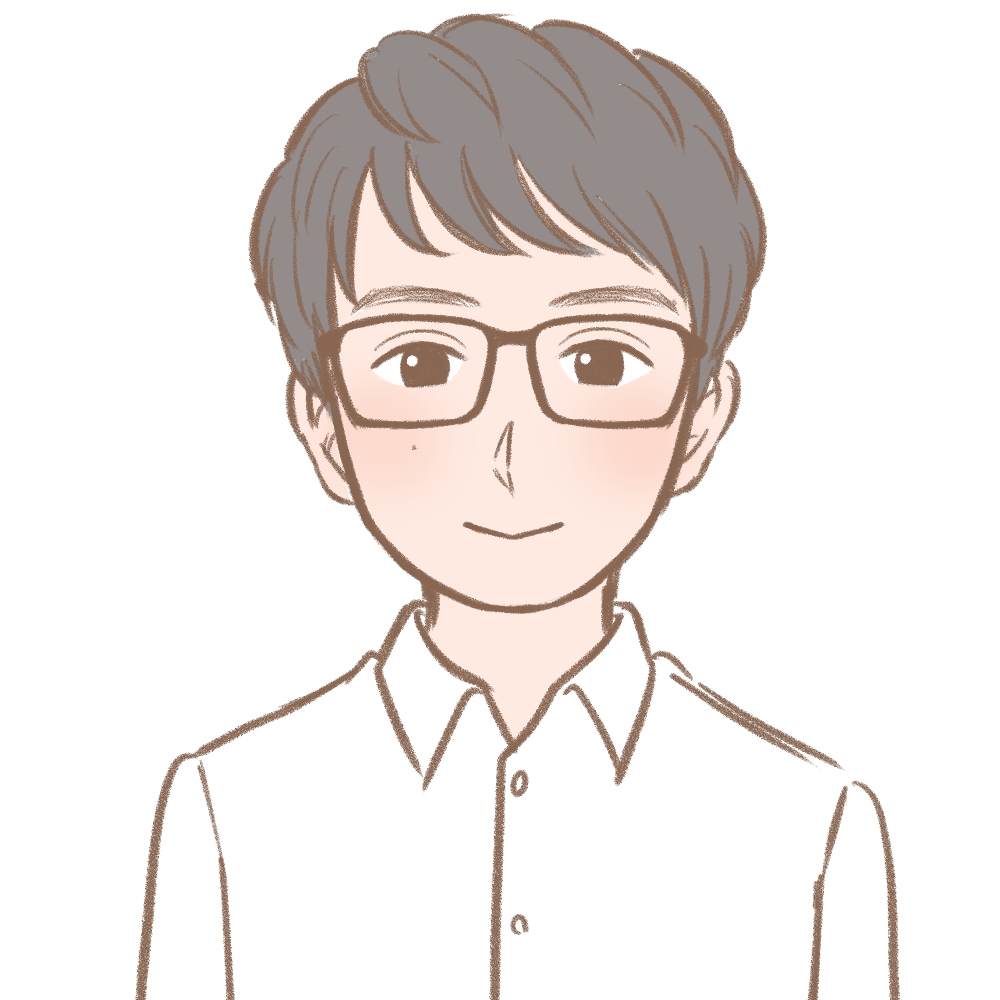
臨床心理士、公認心理師です。5年以上、都内の心療内科や脳神経内科で、うつ病、不安障害、HSP、アダルトチルドレンなど数多くのカウンセリングを経験してきました。HSPの創始者であるアーロン博士の「HSPに精通した専門家プログラム」を修了しています。