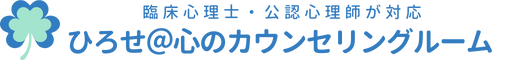強迫性障害(強迫症)の巻き込みにはどう対応すればいい? お互いの関係と症状を悪化させない対処法5選
強迫性障害(強迫症)は、進行すると自分だけでは不安を解消できず、家族や恋人に強迫行為を手伝ってもらおうとすること(巻き込み)が増える病気です。
そのため、本人だけでなく、家族や恋人もつらい思いをするケースが珍しくありません。
中には「頑張って対応してきたけど、症状が重くなるばかりで、どう接してよいのかわからなくなってしまった」と思う人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、強迫性障害を抱える方、支える家族も楽になれる方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
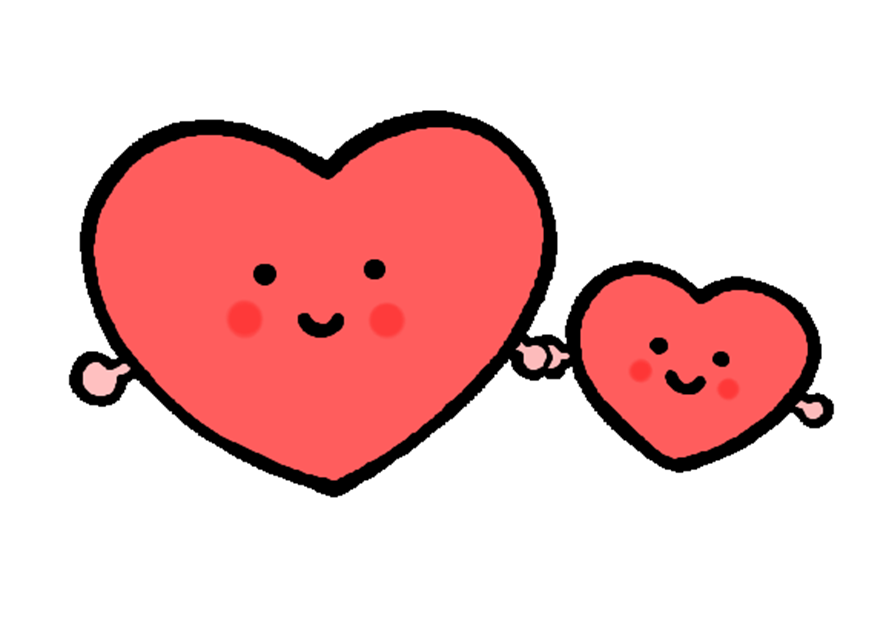
目次
強迫性障害とは?
強迫性障害とは、繰り返し浮かんでくる不快な考え、イメージ(強迫観念)に対し、それを緩和させるために特定の行為(強迫行為)を何度も行ってしまう疾患のこと。
「手が汚れていると感じるため何度も洗う」洗浄恐怖や、「ガス栓が閉じていないかもしれない」と疑い何度も確認する確認行為、さらには縁起に関連した強迫行為などが存在します。
強迫性障害は軽い症状からはじまることが多いですが、次第に強迫観念と強迫行為が重症化し、日常生活に深刻な支障をきたすようになります。
強迫性障害は身近な人が巻き込まれやすい
強迫性障害は、家族や恋人を巻き込みやすい病気です。
「手を洗ってよ」「大丈夫かどうか確認して!」という要求に応じても症状は改善せず、次第に要求が増え、より複雑になっていきます。
頼みごとを断ると本人の不安が強まり、不機嫌になったり、怒ったり、悲しんだりするため、戸惑いを感じる人も多いでしょう。
さらに断った家族は、その反応から罪悪感を抱きやすいので、「間違ったことをしているのでは?」「ひどいことをしているのかな…」などと思い、強迫行為を手伝う方向に進んでも不思議ではありません。

3種類の巻き込み
巻き込みには、以下の3種類があります。
- 質問して保証を求める
本人の不安を和らげるために、「大丈夫?」「誰か傷つけていなかった?」と何度も聞いて、保証を求めるタイプです。
- ルール、行為を強要する
自分のルールに従わせる行為を周囲の人にも要求するタイプ。
「家に帰ってきたら入浴して」「この通路は通らないで」など、様々なパターンが存在します。
- 強迫行為を代行させる
自分の代わりに、家族や恋人へ強迫行為を代行させるタイプです。
たとえば、カギやガスの元栓が閉まっているかどうかを確認させるなどの行為が見られます。
巻き込みは強迫行為の一種ですので、なるべく要求には応じない姿勢で接することが好ましいです。
ですが、強迫行為を手伝ってあげることで一時的には本人の不安が緩和されるので、「できることなら手伝ってあげたい」「断りづらい」といった気持ちも強いでしょう。
次の章からは、強迫性障害を改善するうえで大切な“巻き込み”への接し方について解説していきます。
「巻き込み」に有効な5つの対処法
巻き込みに適切な対応をし、症状を改善させることは想像以上に難しいものです。
大切な関係を拗らせたり、症状を悪化させたりすることも珍しくありません。
ここからは、巻き込みに有効な対処法について紹介していきます。
強迫性障害の性質、特徴を考慮して接する
本人のことを思っている人ほど、相手の要求に応えてしまい、かえって症状を悪化させてしまうのも強迫性障害の特徴の一つです。
かといって要求を拒否することも望ましい対応ではありません。
症状の進行を防ぐためにはどう対応したらよいか、本人と協同的に対話していくことが大切です。
本人も望んでいない反復的な考えや行動は、周りには理解されがたく、孤独を感じやすいです。
なるべく相手の心境に理解を示し、共感する姿勢で接してあげることが相手の助けになります。
ルール、取り決めをつくる
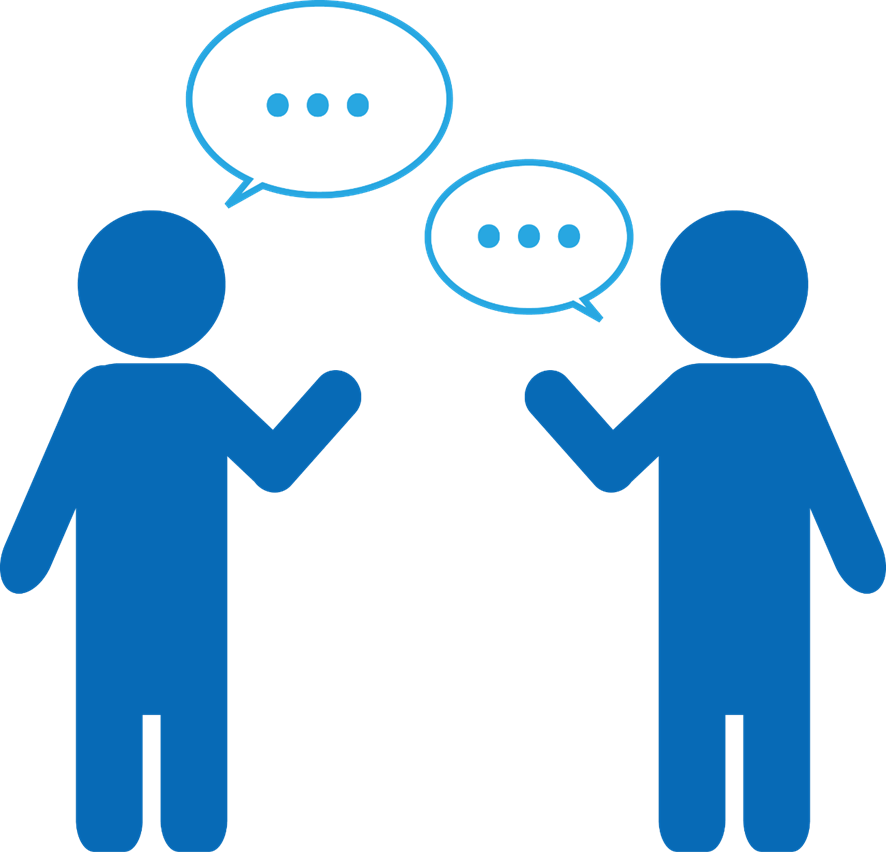
本人からの質問(保証)や確認行為の強要は、あらかじめお互いに話し合ってルールや約束を決めておくと症状の悪化を防ぐことができます。
ルール、取り決めの例としては、「基本1日1回までにする」「強迫行為に関する会話は5分間以内で、それ以上は対応しない」などがあります。
可能であれば、徐々に対応する時間、回数を減らしてくことが理想です。
減らしていくことが困難な場合は、これまで以上の巻き込みには応じないような姿勢で接してみてください。
取り決めをつくるときのポイントは、いきなり厳しめの設定を設けないこと。
強迫行為はある意味、その人が不安を解消させるための大切な行為と言えます。
急に全ての強迫行為を手伝わないといったことをしてしまうと、本人の気持ちがついていかず、関係性が悪化してしまうかもしれません。
無理に急がず、お互いにとって最も受け入れやすい落としどころを探りながら、一緒に取り決めを行っていくといいでしょう。
強迫行為を指摘してあげる
「それは巻き込み、強迫行為かも。」
「強迫観念と客観的事実がごっちゃになっているよ。」
などと声をかけ、本人が冷静さを取り戻すきっかけづくりも症状の改善に有効です。
強迫行為、巻き込みが習慣化して日常生活に溶け込んでいると、強迫観念に侵されていることに案外気づきにくくなっているものです。
強迫観念が強くなっているときは、客観的な物事の捉え方がうまくできず、合理的な判断が難しくなっています。
あえて「それは強迫行為、巻き込みである」と指摘してあげることで、本人が強迫観念にとらわれていることに気づき、自らブレーキを掛けられるかもしれません。
お互いのプライベートな時間を大切にする
症状が進行すると、大切な人をサポートするために自然と一緒にいる時間も長くなりがち。
もちろん、一緒に過ごすことも治療的には大切で、お互いの不安も和らぐかもしれません。
しかし、一緒にいる時間が長くなることで巻き込みが生じる機会も増えてしまいます。
巻き込み行為は治療上よくないことが分かっていても、巻き込みが生じる機会がすぐ目の前にあれば、気力で我慢するのは難しいでしょう。
今は自分の時間を大切にする余裕がないかもしれないですが、つらいときこそ巻き込みの機会を増やしすぎないよう、プライベートな時間を大切にしてください。
治療は無理に参加させなくても良い
家族やパートナーとしては、大切な人の強迫行為を治してあげたい思いから、半ば無理やり治療を押し付けてしまうこともあるかもしれません。
ただ、最も大切なのは本人の気持ちであり、最初は押し付けによって改善できたとしても、途中から挫折したり、強い反発心が生まれたりする原因となってしまうことがあります。
「できることなら治したい」という気持ちは本人も強いと考えられるので、その気持ちを支持してあげることが大切です。
【強迫性障害の巻き込み】こんなときはどうする?
巻き込みに有効な対処法を意識していても、ときには症状が改善されず、新たな問題に直面することもあるかもしれません。
ここでは一例として、強迫性障害によって暴力が生じる場合、家族が限界を感じた場合の対処法を紹介していきます。
反発が強く、暴力が生じてしまう場合は?
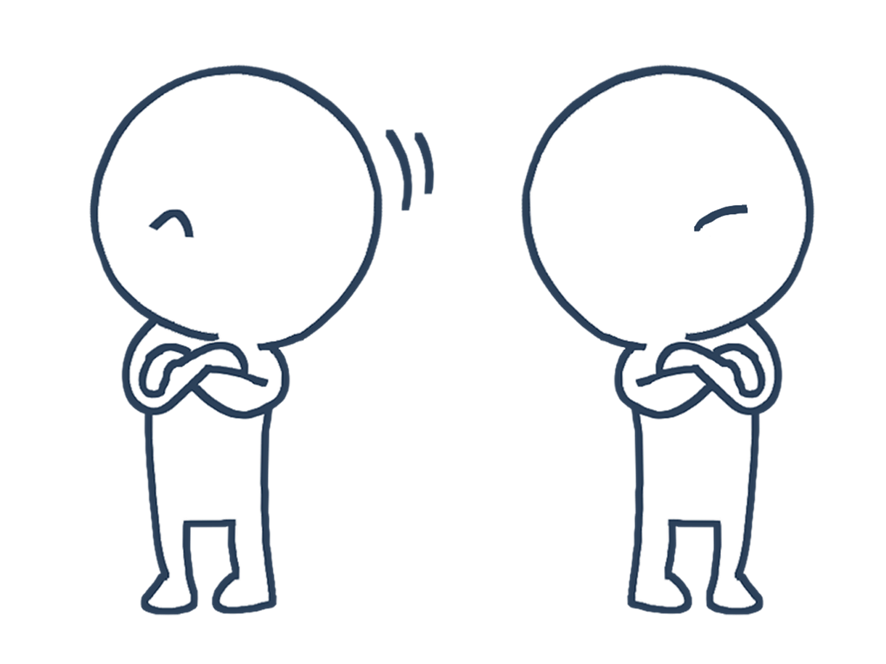
強迫性障害は、苦しみのあまり、性格が変わったかのように攻撃的になってしまう方も多く見られます。
暴言、叩く、殴るといったことが生じる場合は、無理に巻き込まれる回数を減らそうとしなくても大丈夫です。
ただ、優しい言葉をかけながらも、なるべく毅然とした態度で、「暴力はいけない」というメッセージを伝えてください。
主治医がいれば、相談すること、通院していなければ、通院のきっかけとして取り扱うことも良いでしょう。
あらかじめ、「最悪の場合は、警察への通報もあり得る」という認識をお互い共有しておくことが必要なときもあります。
緊迫した雰囲気になってしまった際は、「強迫性障害の症状で怒りっぽくなっているんだ」と心の中でつぶやき、なるべく受け流して、ダメージを受けないようにすることがポイントです。
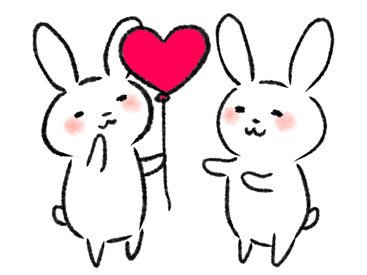
巻き込みの対応に限界を感じた場合は?
本人の巻き込み行動が増え、対応に心が折れ、限界に達している人も多いと思います。
過度な要求は、本人の性格ではなく、強迫性障害の症状です。
最も優先すべきことは、お互いの健康と体調であるため、無理に完璧な対応をする必要はありません。
また、うまく対応できないと感じる自分を責めないようにしましょう。
大切な人の強迫性障害を改善させるには、焦らずに付き合っていくことが大切です。
また、ひとりで抱え込み過ぎないよう、ときには周囲の人や専門家に頼ってみてください。
まとめ:お互いを大切に、無理せず強迫性障害と向き合う
巻き込みは本人の支えになっている部分もあり、うまく接しようとしても、失敗に終わることも珍しくありません。
強迫性障害の症状は頑張って接していても、進行してしまうことがあります。
悪いのは誰でもなく、強迫性障害の症状です。
たとえ状況が悪化してしまったとしても、自分を責めないことを心がけましょう。
今回ご紹介した対処方法を参考にして、様々な対応を試してみてください。
当カウンセリングルームでは、強迫性障害(強迫症)を対象としたカウンセリングを行っています。
まずはお気楽にご相談ください。
11月先着3名様
初回カウンセリング
45分 5,000円
※はじめての方は初回カウンセリングをお申込みください。
※初回はオンラインでカウンセリングを行っています。Zoom・Skype・Line通話でのカウンセリングが可能です。
※初回カウセリングでは、現在のあなたの状態をお伺いして、今後の目標や方針を決めていきます。
LINEでのご相談
愛着障害や強迫性障害、不安障害のご相談を受け付けています。
HSPやアダルトチルドレンのお悩みの方やカウンセリングご希望の方は、友達追加ボタンを押して、メッセージをお送りください。
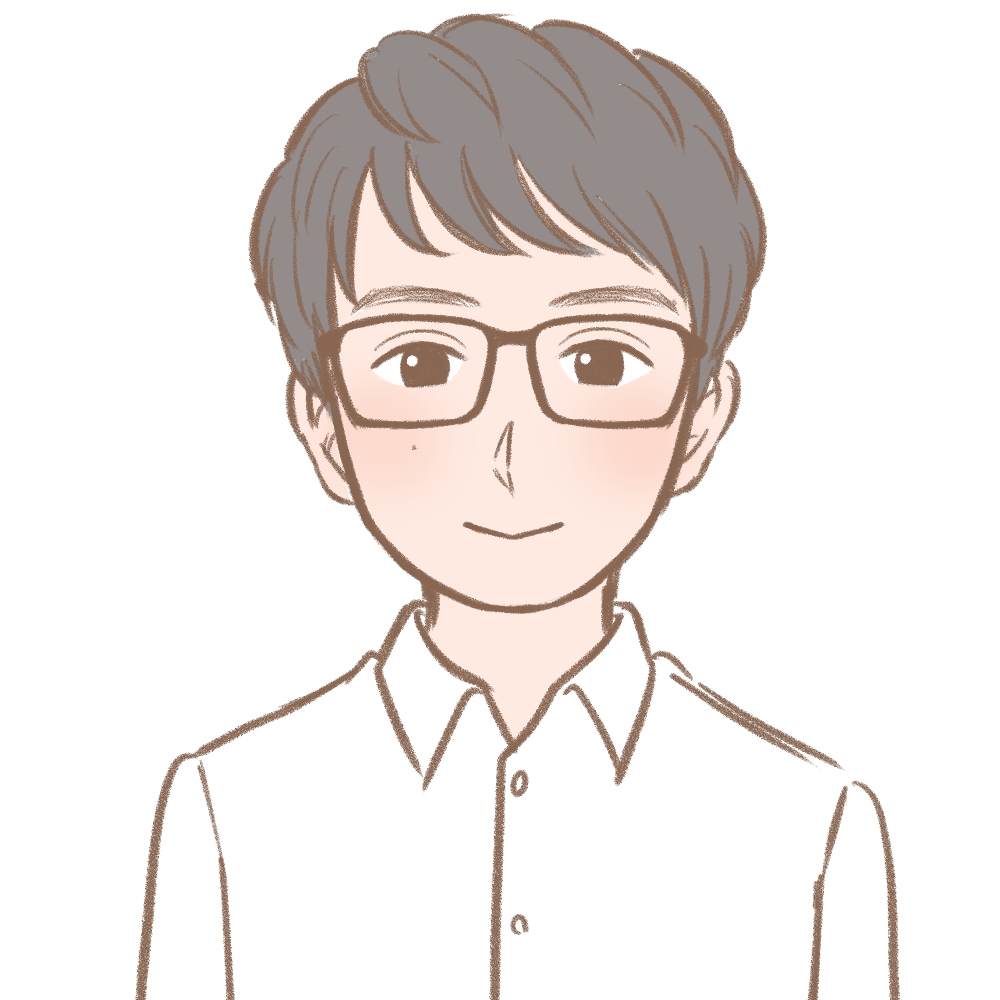
臨床心理士、公認心理師です。5年以上、都内の心療内科や脳神経内科で、うつ病、不安障害、HSP、アダルトチルドレンなど数多くのカウンセリングを経験してきました。HSPの創始者であるアーロン博士の「HSPに精通した専門家プログラム」を修了しています。