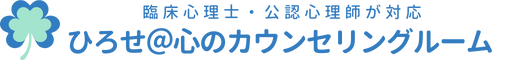【強迫性障害】強迫行為を繰り返すと不安が強まるのはなぜ? 不安改善のポイントを解説
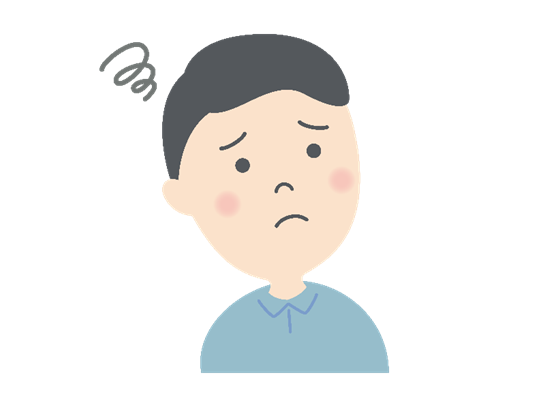
「誰かを傷つけてしまう」「ガスが漏れて火事になってしまう」など、嫌な思考、イメージがなかなか頭から離れない。
強迫性障害は、非現実的な考えだとわかってはいても、なかなかやめられない疾患です。
最初は不快なイメージに何とか対処できていたけれど、不安と強迫行為は強まるばかりで、一向に改善する気配がないという人はとても多いと思います。
この記事では、強迫性障害を抱えた方の不安が強まる理由とその対処法について解説していきます。
改善の気配がなくこの先不安という方は、最後まで読んでみてください。
目次
強迫性障害について
強迫性障害とは、不快な思考、イメージが何度も浮かび、それを阻止しようとあらゆる手段(強迫行為)を試みてしまう疾患のことです。
自分のせいで悪いことが起こる、自分が何かをしてしまうといったように、自分の責任感が極度に強くなってしまう病気でもあります。
正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内の機能障害、遺伝的要因、ストレスの多い環境、完璧主義などが関係しているとされます。
不安が高くなってしまう理由とは

「人を傷つけてしまいそう」「ガス栓を閉め忘れたかもしれない」といった考えが浮かぶことは誰にでも起こりえることです。
ですが、強迫性障害の場合は、考えの受け止め方に違いがあり、自分で浮かべた悪いイメージにとらわれてしまう傾向があります。
また、不快な考えが浮かぶことはいけないことだと思い、無理にコントロールしようとすることも特徴です。
強迫性障害の方の思考はリアリティーが高いです。リアルにイメージするあまり自分の責任だと思い、不確実性の高い出来事も何とか阻止しようとコントロールしてしまいます。
「考えないようにする」「大丈夫なはず」というように無理に考えてコントロールしようとするとかえって、頭から離れず、印象に強く残ってしまう性質があります。
さらに、思考は現実を現したものではなく、あくまで頭の中のイメージなので、考えれば考えるほど、客観性を失い、恐ろしいものへと成長していってしまうでしょう。
このような性質から、不快な思考、イメージに集中し続けてしまうことで、不安が持続し、次第に強くなっていってしまうのです。
不安を改善させるうえで大切なポイント
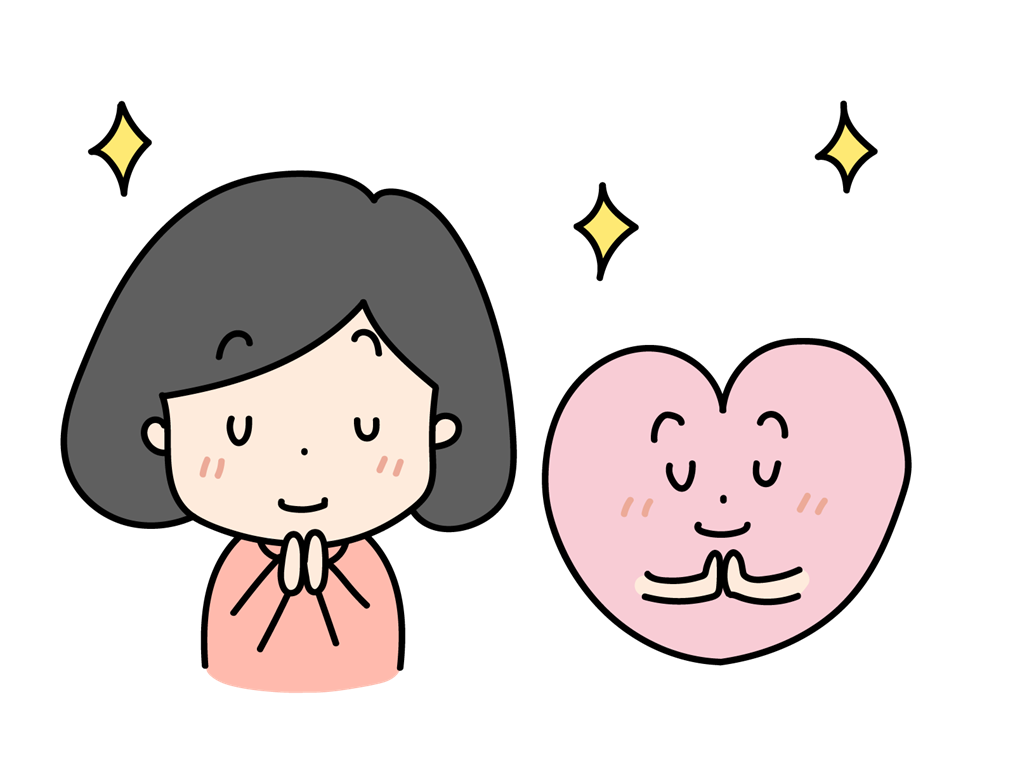
嫌なイメージが浮かび不安を感じてしまうのは正常なことです。しかし、考え続けることでイメージが深刻化し、最終的には手に負えなくなってしまいます。
そのため、強迫観念や浮かんでしまった考え、イメージとどのように向き合うかがポイントです。
ここからは頭から離れない考えから距離を置き、不安を緩和させるうえで大切なポイントについて解説します。
リアリティーのあるイメージでも、それは強迫観念であることを意識する
考えは、現実を忠実に表したわけではありませんが、現実のようなリアリティーがあります。
「私のせいで誰かが難病にかかる」「傷つけてしまう」という考えが、非現実的だとわかっていても、実際に起きるかのように感じてしまうかもしれません。
調子が悪いときは、強迫観念に飲み込まれ、深く考え込んでしまうことは仕方がない部分もあると思います。精神科医であっても、強迫性障害を抱えると抜け出せなくなる例があるくらいです。
ですが、そのようなときは、これは強迫観念だということに気づき、それを意識しながら考えるように試みてください。
その視点を持ち続けることが、症状の悪化を防ぎ、改善につながります。
浮かんだ強迫観念を問題視し、自分を責めない
不快なイメージによって、ときに自分が恐ろしい人物やおかしな人間になってしまうのではないかと思うこともあるかもしれません。
しかし、重要なのは、これらの思考や不安はあなたの本質ではなく、症状の一部だと理解することです。
強迫観念のような侵入思考は必ずしもあなたの価値観、人間性と一致するものではありません。
むしろ、それらとは全く異なる場合が多いです。
思考、イメージから抜け出し、距離を置けるようになれれば「本当の自分はそんなことは到底できない」ということに気づくでしょう。
強迫行為を時間で制限する
強迫行為は不快な考えを和らげるために行う対処ではありますが、その解決方法そのものが問題となり、生活に著しい支障をきたすことも特徴です。
強迫観念に繰り返し注意を注ぐことは、最初は生産的な問題解決のように感じられるかもしれません。
実際、強迫行為は、不安を一時的に改善させるため、どうしてもやめられない一面もあるでしょう。
ですが、行えば行うほど物足りなくなり、強迫行為が増え続けてしまいます。
確認行為や洗浄行為は、次第に一回の精度が低下し、問題解決からそれを行うこと自体に目的がシフトします。
そして、それを行うことが普通の感覚となり、たくさん強迫行為を行っているからこそ、強迫観念が現実にならずに済んでいるというような錯覚にも陥りやすくなります。
対処しようとがんばり過ぎると、返って強迫性障害の症状を維持する支えになってしまうのです。
そのため、強迫行為をしてしまう時間を制限し、行為を増やさないように努めるとコントロールしやすくなるのでおすすめです。
強迫観念が頭に浮かぶかどうかはコントロールできないかもしれませんが、それに対してどう反応するかはコントロールをすることができます。
おわりに
強迫性障害は、非常に困難な疾患ですが、適切に対処することで、症状を軽減し、日常生活を取り戻すことが可能です。
強迫性障害の症状は、あなたの人生の一側面に過ぎず、あなたの本質を示すものではありません。
専門家のサポートを受けることで、より効果的に症状と向き合い、改善への道筋を見出すことができます。
当ルームでは、強迫性障害を対象としたカウンセリングを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
11月先着3名様
初回カウンセリング
45分 5,000円
※はじめての方は初回カウンセリングをお申込みください。
※初回はオンラインでカウンセリングを行っています。Zoom・Skype・Line通話でのカウンセリングが可能です。
※初回カウセリングでは、現在のあなたの状態をお伺いして、今後の目標や方針を決めていきます。
LINEでのご相談
愛着障害や強迫性障害、不安障害のご相談を受け付けています。
HSPやアダルトチルドレンのお悩みの方やカウンセリングご希望の方は、友達追加ボタンを押して、メッセージをお送りください。
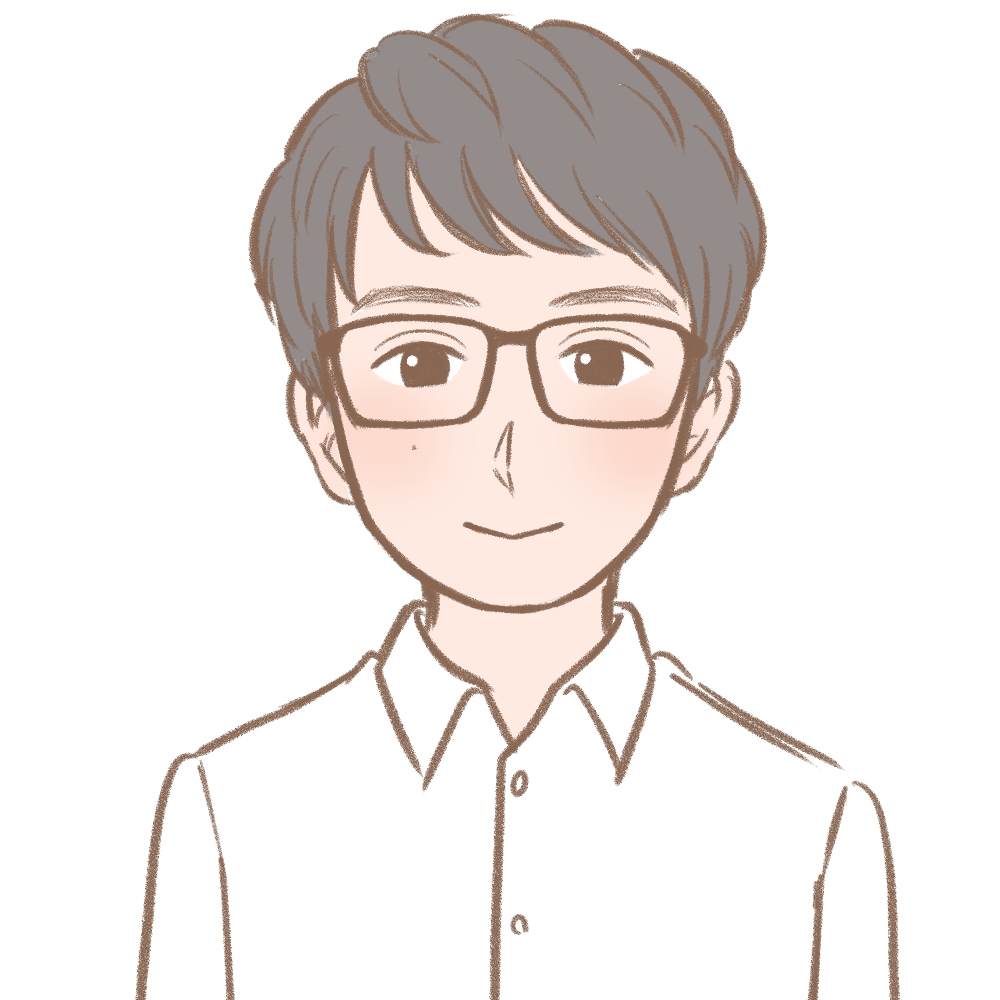
臨床心理士、公認心理師です。5年以上、都内の心療内科や脳神経内科で、うつ病、不安障害、HSP、アダルトチルドレンなど数多くのカウンセリングを経験してきました。HSPの創始者であるアーロン博士の「HSPに精通した専門家プログラム」を修了しています。